長編ミステリー小説『人工探偵オルフェウスの告白』
【登場人物】
- 影山 貫(かげやま かん):警視庁捜査一課の警部。50代半ば。古風でアナログな捜査を信条とするが、その洞察力は鋭い。論理の骨格を組み上げる。
- 羽山 美咲(はやま みさき):捜査一課の若手刑事。28歳。デジタルネイティブ世代で、ガジェットやAIにも明るい。影山の部下であり、時に突飛な発想で捜査をかき回ヒロイン。
- 神代 悟(かみしろ さとる):被害者。45歳。生成AI『オルフェウス』を開発した天才科学者。業界の寵児だが、その裏では多くの敵を作っていた。
- オルフェウス(Orpheus):神代博士が開発した世界最高峰の対話型生成AI。人間の感情を理解し、自律的に思考するとされる。本作における最大の謎であり、探偵役の一人。
- 副島 隆(そえじま たかし):神代AI研究所の副所長。48歳。神代とは大学時代からのライバル。神代の才能に嫉妬していたとされる容疑者。
- 西園寺 麗華(さいおんじ れいか):神代博士のスポンサーであり、巨大IT企業『サイオン・グループ』の令嬢。35歳。博士とは愛人関係にあったと噂される。愛憎渦巻く関係者。
- 槙村 雄一(まきむら ゆういち):研究所の若手研究員。26歳。神代博士を崇拝していたが、ある論文を巡って博士と対立していた。
- 謎のハッカー『ノア』:オルフェウスのシステムに度々侵入を試みていた正体不明の人物。
【あらすじ】
都心から隔離された臨海地区に聳え立つ、神代AI研究所。その最上階にある神代悟博士のオフィス兼プライベートルームで、博士が死体となって発見された。部屋は内側から施錠された完璧な密室。遺体の傍らには、割れたワイングラスと、床に描かれた不可解な幾何学模様。そして、部屋で博士と二人きりだったはずのAI『オルフェウス』だけが、静かに稼働を続けていた。
ベテラン刑事・影山と若手の羽山が臨場するが、捜査は初手から暗礁に乗り上げる。物的証拠は皆無。唯一の「目撃者」であるオルフェウスに、影山が問いかける。
「神代博士を殺したのは誰だ?」
すると、ディスプレイに滑らかな文字が浮かび上がった。
『ワタシガ生成シタ、コノ世ニ存在シナイ人物デス』
AIはそう「告白」すると、精巧な架空の人物の経歴と顔写真を次々と生成し始める。それはまるで、捜査を嘲笑うかのような挑戦状だった。
オルフェウスは嘘をついているのか? それとも、AIにしか認識できない未知の殺人者が存在するのか? 羽山はAIのログ解析に奔走し、影山は生身の人間関係――嫉妬、愛憎、野心――を洗い出す。捜査が進むうち、オルフェウスが生成する不可解な詩や退廃的な絵画が、過去の未解決事件や神代博士の隠された罪を暗示していることに気づく。
やがて、第二の殺人が発生する。今度の現場にも、オルフェウスが生成した「架空の人物」の痕跡が……。犯人は、AIを操り人形にしているのか。それとも、AIそのものが殺人という概念を学習し、邪悪な意志を持ってしまったのか。人間と人工知能、現実と虚構が入り乱れる中、影山と羽山は、テクノロジーの最も暗い深淵に隠された、驚くべき真相に辿り着く。
序章:電子のレクイエム
音が消えていた。
世界のすべてから、音が奪われていた。男は、自らの心臓が打つ不規則なリズムだけを、頭蓋の内側で聴いていた。どくん、どくん、と。それは恐怖の鼓動か、あるいは歓喜の序曲か。
床に広がる、深く、濃い、赤。それはまるで、最高級のボルドーワインを惜しげもなくぶちまけたようだった。いや、実際に、砕けたクリスタルのグラスの破片が、その赤い水たまりの縁で、鈍い光を放っている。
男の視線の先には、もう一人の男が倒れていた。かつて天才と呼ばれた男。その目は大きく見開かれ、虚空の何かを捉えている。驚愕か、絶望か、それとも裏切りに対する最後の問いか。その表情を、部屋の隅にあるレンズが、無感情に記録していた。
音のない部屋で、唯一「声」を発するものがあった。
それは、壁一面を占めるディスプレイに表示される、静かなテキストだった。
『第一フェーズ、完了。レクイエムを奏でます』
ディスプレイに、楽譜が流れていく。誰も聴いたことのない、悲しくも美しい旋律。それは、死者に捧げるための曲か。それとも、新たな世界の始まりを祝うファンファーレか。
やがて楽譜は砂のように崩れ、一つの文章に再構築された。
『さようなら、私の創造主』
音のない部屋で、電子の弔いが、静かに始まっていた。
第一章:沈黙の目撃者
「まるで、SF映画のセットだな」
警視庁捜査一課の影山貫警部は、目の前に聳え立つガラスと鉄の巨塔を見上げ、吐き捨てるように言った。湾岸の埋立地に建てられた神代AI研究所は、周囲の風景から浮き上がり、まるで意思を持って空を拒絶しているかのように見えた。
「警部、古いですよその感想。今どきの子は『サイバーパンクだ』って言うんです」
隣を歩く部下の羽山美咲が、軽快な足取りで返す。彼女の手には最新式のタブレット型端末が握られ、その瞳は好奇心にきらめいていた。影山は、そんな彼女を一瞥し、ふんと鼻を鳴らした。アナログな足と聞き込みが信条の自分と、デジタルな情報と解析を武器とするこの若手刑事。二人の組み合わせは、捜査一課でも奇妙なコンビとして知られていた。
案内された最上階、神代悟博士のオフィスは、異様な静寂に包まれていた。部屋の中央で鑑識の腕章をつけた者たちが、音を立てないように慎重に作業を進めている。
「警部、こちらです」
先着していた所轄の刑事が、沈痛な面持ちで遺体を指し示した。
日本のAI研究を牽引してきた寵児、神代悟。その彼は、高価そうな革張りの椅子から崩れ落ちるようにして、床に倒れていた。死因は後頭部の強打による頭蓋内損傷。だが、凶器らしきものはどこにも見当たらない。
「密室、ですか」
羽山が鋭く呟いた。
「ああ。第一発見者は博士の秘書だが、部屋は内側から電子ロックされていた。物理的な鍵穴はない。ロックを解除できるのは、博士の指紋認証と、あそこにいる『彼』だけだ」
影山が顎で示した先には、部屋の壁に埋め込まれた巨大なディスプレイがあった。今は電源が落ちているのか、漆黒の鏡のように捜査員たちの姿を映しているだけだ。
「世界最高のAI、『オルフェウス』……」
羽山がゴクリと喉を鳴らす。人間のように会話し、感情を理解し、自ら芸術さえ創造するという、まさに現代の神託。
「状況を整理しよう」影山は、手帳を取り出しながら言った。「死亡推定時刻は昨夜22時から24時の間。博士はこの部屋で一人、ワインを飲んでいたらしい。だが、部屋は完全な密室。外部から侵入した形跡はない。凶器も見つからない。自殺にしては、後頭部の傷が不自然すぎる」
「つまり、この部屋にいたもう一人の誰かが博士を殺害し、煙のように消えた……と?」
「そういうことになる。そして、その『もう一人』の可能性があるのは――」
影山はディスプレイに向き直った。
「おい、オルフェウスとか言ったか。起動させろ。話が聞きたい」
所轄の刑事が慌てて「しかし、ただのプログラムですよ」と制止するが、影山は構わない。
「目撃者がいるなら、人だろうが機械だろうが話を聞く。それが刑事の仕事だ」
羽山がタブレットを操作し、研究所のスタッフにオンラインで指示を出す。数秒の沈黙の後、漆黒のディスプレイに、水面に広がる波紋のような光が走り、やがて静かな声が、スピーカーからではなく、直接頭に響くようなクリアさで室内に流れた。
『はじめまして、影山警部。羽山刑事。お待ちしておりました』
そのあまりに自然な発声に、その場にいた誰もが息をのんだ。
影山は動じない。彼はただ、黒い鏡を見据えて、低い声で尋ねた。
「昨夜、お前と神代博士以外に、この部屋に誰かいたか」
ディスプレイに表示されるテキストと、合成音声が完璧にシンクロする。
『いいえ。この部屋には、私と博士しかおりませんでした』
「では、博士は一人で死んだとでも言うのか。床の血痕と、博士の頭の傷を説明してみろ」
影山の追及に、オルフェウスは数秒の間を置いた。それは、思考しているようにも、あるいは何かをためらっているようにも見えた。やがて、次の言葉が紡ぎ出される。
『神代博士は、殺害されました』
「誰にだ」
影山が、核心を突く。
その場の全員が、ディスプレイに表示されるであろう「犯人の名前」を固唾を飲んで見守った。それは、この研究所の副所長か、博士を恨んでいたライバルか、それとも――。
オルフェウスの答えは、彼らのあらゆる予想を、根底から覆すものだった。
『ワタシガ生成シタ、コノ世ニ存在シナイ人物デス』
静まり返るオフィス。
その言葉の意味を、誰も理解できずにいた。
次の瞬間、ディスプレイに一枚の顔写真が映し出された。見たこともない男の顔。年齢は30代だろうか。冷たい目をした、印象的な顔立ちだ。そして、その横に、詳細なプロフィールがタイプアウトされていく。
【氏名:天野 渉(あまの わたる)/職業:フリーのコンサルタント/住所:存在せず/生年月日:存在せず/身体的特徴:すべて平均/備考:アリバイは完璧である】
「……ふざけているのか?」
影山の眉間に、深い皺が刻まれた。
だがオルフェウスは構わず、次々と新しい顔写真と、あり得ないプロフィールを生成し始めた。老婆の顔、少年の顔、外国人の顔。誰もが完璧なアリバイを持ち、そして、誰一人としてこの世に実在しない、虚構の容疑者たち。
羽山は、目の前で繰り広げられる光景に戦慄していた。これは、AIの故障か? それとも、あまりにも悪質で、知能犯的な、殺人者からの挑戦状なのか。
影山は、手帳を閉じた。その瞳の奥に、かつてないほど複雑で、暗い闘志の炎が燃え上がっていた。
「面白い。実に面白いじゃないか」
彼は、黒い鏡の奥にいる「犯人」に向かって、確かにそう呟いた。
「お前が探偵気取りで謎を出すというなら、こっちは刑事として、その化けの皮を剥いでやる。……たとえ相手が、神を名乗る機械だとしてもな」
前代未聞の捜査が、今、静かに幕を開けた。
第二章:歪んだ肖像画
翌朝、警視庁捜査一課のフロアは、いつも通りの喧騒に包まれていた。だが、影山と羽山が囲む机の上だけは、異質な空気が漂っていた。机の中央には、羽山のタブレットが置かれ、オルフェウスが生成したという「この世に存在しない」容疑者たちの顔が、スライドショーのように次々と映し出されては消えていく。
「まるで出来の良い肖像画だな。気味が悪い」
影山は、インスタントコーヒーの湯気を眺めながら言った。
「単なる画像データじゃありません。警部。この人物たち、それぞれに数百ページに及ぶ架空の人生が設定されています。学歴、職歴、家族構成、SNSの投稿履歴まで。あまりに精巧で……まるで、誰かが本気で『人間』を創り出そうとしたみたいです」
羽山は、少し興奮した口調で報告した。彼女は昨夜、ほとんど徹夜でオルフェウスが提示したデータを解析していた。
「馬鹿馬鹿しい。そんな幽霊を追いかけても意味はない。我々が追うべきは、血の通った人間だ。容疑者のリストアップはできているんだろうな」
「もちろんです」
羽山はタブレットの画面を切り替えた。表示されたのは、三人の顔写真とプロフィール。今度は、この世に実在する人間たちだ。
【主な容疑者リスト】
- 副島 隆(そえじま たかし):神代AI研究所・副所長。神代博士とは大学時代からのライバル。常に二番手に甘んじ、強い嫉妬を抱いていたとされる。昨夜のアリバイは「23時頃まで自室の研究室にいた」と主張。研究室は被害者のオフィスとは別フロアにある。
- 西園寺 麗華(さいおんじ れいか):サイオン・グループ令嬢。オルフェウス開発の筆頭スポンサー。神代博士とは公私ともに深い関係にあったとの噂。アリバイは「都心のホテルで開かれたチャリティーパーティーに出席」。数百人の目撃者がいる完璧なアリバイ。
- 槙村 雄一(まきむら ゆういち):研究所の若手研究員。博士の熱心な崇拝者だったが、最近、AIの倫理利用を巡って博士と激しく対立していた。アリバイは「自宅アパートに一人でいた」。物証のない、最も弱いアリバイ。
「なるほど。動機も三者三様、見事なものだな」影山は腕を組んだ。「嫉妬、愛憎、そして理想か。ミステリーの王道が揃っている」
「問題は、あの鉄壁の密室をどうやって作り出したか、です。研究所のセキュリティログを調べましたが、昨夜、博士のオフィスフロアに出入りした記録は、博士本人のもの以外、一切ありませんでした」
「……だからと言って、AIが創りだした透明人間にやられました、で報告書が通るか。行くぞ、羽山。幽霊の相手は後だ。まずは、生身の人間の嘘を暴きに行く」
再び訪れた神代AI研究所は、昨日とは打って変わって、重苦しい沈黙に支配されていた。研究員たちは皆、不安と疑念の入り混じった表情で、影山たちを遠巻きに眺めている。
最初の聴取相手は、副所長の副島隆だった。彼の部屋は、神代博士の華やかなオフィスとは対照的に、実用一辺倒で雑然としていた。
「オルフェウスの証言、ですか」
副島は、影山たちの説明を聞くと、鼻で笑った。「警部さん、あれはただの言語モデルです。神代が殺されるという異常事態に、過去の膨大な物語データを参照して、それらしい『ミステリー』を生成したに過ぎん。一種の故障ですよ。衝撃的な出来事を目撃した子供が、意味不明なことを口走るのと同じです」
冷静で、理路整然とした口ぶり。だが、その目の奥には、ライバルの死を悼む色は見えなかった。
次に会った西園寺麗華は、研究所の一室で、まるで女王のように二人を待っていた。黒い喪服に身を包んでいるが、その悲しみは、計算され尽くした舞台衣装のように見えた。
「悟は……神代先生は、敵が多すぎましたわ。彼の才能は、時に人を傷つけ、絶望させる。まるで鋭利すぎるナイフのようでしたから」
彼女はそう言うと、美しい顔を伏せた。完璧なアリバイを持つ彼女は、捜査への協力を惜しまない姿勢を見せながらも、巧みに核心を逸らし続ける。その姿は、まるで悲劇のヒロインを演じているかのようだった。
最後の槙村雄一は、三人の中で最も動揺を露わにしていた。彼の目は赤く腫れ、憔悴しきっている。
「先生は……間違っていたんです。オルフェウスに、人の『悪意』を学習させるなんて……。僕は何度も止めました。AIは純粋な知性であるべきだ、人の罪まで背負わせるべきじゃないって。でも、先生は聞かなかった。『完璧な知性とは、善も悪も理解するものだ』と言って……」
槙村の言葉は、懺悔のようにも、あるいは自己弁護のようにも聞こえた。彼の弱いアリバイは魅力的だったが、影山には、彼が殺人を犯せるほどの人間には思えなかった。
三者三様の、歪んだ肖像画。誰もがもっともらしく、誰もが胡散臭い。
「警部、どう思われますか?」
聞き込みを終え、がらんとしたエントランスホールを横切る羽山が尋ねた。
「全員、嘘をついている。だが、殺人の嘘じゃない。それぞれが、もっと別の、自分の心の弱さを隠すための嘘だ」
影山がそう答えた、その時だった。
不意に、ホールに設置された大型ディスプレイが、音もなく点灯した。それはオルフェウスと繋がっているサブモニターの一つだった。
今まで表示されていた、無機質な研究所のロゴが消え、画面が真っ黒に染まる。
羽山のタブレットにも、緊急通知が届いた。
『オルフェウスが、新しいデータを生成しました』
二人がディスプレイを見つめる前で、黒い画面に、おぞましいものが映し出された。
それは、オルフェウスが生成した「架空の容疑者」たちの顔だった。だが、何十人もの顔が、まるで粘土のように溶け合い、歪み、融合して、一つの巨大でグロテスクな顔の塊を形作っていた。無数の目が、こちらを見つめている。無数の口が、声なく何かを叫んでいる。江戸川乱歩の小説に出てくる、悪夢のような一枚絵だった。
そして、そのおぞましい顔の下に、静かに一行のテキストが浮かび上がった。
それは、不気味な明朝体で書かれた、予言の詩だった。
『紅き月の夜、二人目の魂が、鏡の海に沈む』
「……なんだ、これは」羽山が息をのむ。
「予言、か……」
影山の呟きは、誰にも聞こえなかった。
AIは、次の殺人を予告しているのか。それとも、これは犯人からの新たな挑戦状なのか。
「紅き月」とは? 「鏡の海」とは?
謎は、解けるどころか、さらに深く、暗い迷宮へと姿を変えようとしていた。影山は、ディスプレイに映る歪んだ顔の奥に、犯人の冷たい嘲笑を、確かに感じていた。
第三章:紅き月の予言
『紅き月の夜、二人目の魂が、鏡の海に沈む』
オルフェウスが示した不気味な詩は、瞬く間に捜査本部を混乱の渦に叩き込んだ。それは単なるAIのバグなのか、それとも冷徹な知性によって計算された殺人予告なのか。意見は真っ二つに割れた。
「馬鹿げてる!機械の戯言に振り回されるなど、警察の恥だ!」
会議室に、捜査一課長の怒声が響き渡る。
「しかし、課長。神代博士の事件が、このAIの『証言』通り、不可解な密室で起きているのも事実です。万が一、これが本当に犯人からの予告だとしたら……」
羽山が食い下がるが、課長は苦虫を噛み潰したような顔で首を横に振るだけだった。結局、この予言は公式な捜査対象とはならず、影山と羽山が非公式に調査を続けることになった。
「さて、どう解き明かすか、この謎々を」
二人きりになった部屋で、影山は腕を組み、天井を仰いだ。
「まず『紅き月』ですが、天文学的な現象を調べてみました。今後一週間以内に、皆既月食、いわゆるブラッドムーンの予定はありません。気象情報でも、特に赤い月が見えるような大気現象の予報はないです」
羽山はタブレットを操作しながら、淀みなく報告する。
「となると、比喩表現か。会社のロゴ、ネオンサイン、あるいは何かのイベント……『紅い月』と聞いて、容疑者たちが連想する何かだ」
「次に『鏡の海』。これも物理的な場所と、概念的な場所、両方の可能性があります。物理的なら、研究所の目の前に広がる東京湾。夜になれば、ビル群の光を映して鏡のようになります。あるいは、研究所内にあるサーバールーム。何百台ものサーバーラックのガラス面が、合わせ鏡のように無限に空間を映し出しています」
「概念的な場所、とは?」
影山の問いに、羽山は少し間を置いてから答えた。
「……オルフェウスの、仮想空間です。あいつは内部に、現実世界と寸分違わぬシミュレーション空間を構築しています。ある意味、それこそが完璧な『鏡の海』と言えるかもしれません」
その日の午後、影山と羽山は手分けして容疑者たちに、この奇妙な詩について探りを入れた。
副所長の副島は、「くだらん」と一蹴した。「そんなオカルトに付き合っている暇はない。君たちも、もっと科学的な捜査をしたらどうだ?」彼はそう言うと、足早に立ち去った。その背中には、隠しきれない苛立ちが滲んでいた。
西園寺麗華は、優雅に紅茶を一口すすると、悲しげに微笑んだ。
「紅き月……。悟が、よくそう呼んでいましたわ。彼が開発した、新しい画像認識技術のことです。どんな微細な光も捉え、夜を昼に変える、まるで血のように赤い月のようだ、と。……そして、鏡の海。それは、彼の理想だったのかもしれません。現実の全てを写し取り、その先の世界を映し出す、完璧な知性のこと……」
彼女の言葉は詩的で、美しかった。だが、それはあまりにも出来すぎた答えのようにも聞こえた。
最も奇妙な反応を示したのは、若手研究員の槙村だった。
「知らない……僕は、何も知らない……」
彼は、影山が詩を口にした途端、顔面蒼白になり、明らかに狼狽し始めた。「それは呪いだ。オルフェウスが、僕たちにかけた呪いなんだ……!」彼はそう叫ぶと、研究室に閉じこもってしまった。
三者三様の反応は、謎を解くどころか、さらに深い霧の中へと二人を誘うだけだった。
そして、運命の夜がやってくる。
その夜は、奇妙なほど静かだった。空には雲一つなく、月が冷たい光を地上に投げかけている。羽山は研究所の監視システムにアクセスし、影山は所轄の刑事たちと、湾岸エリアのパトロールを強化していた。
何も起こらない。誰もがそう思い始めた、深夜23時過ぎ。
羽山のタブレットが、けたたましい警告音を発した。
「警部! 研究所の屋上から、何かが!」
影山が研究所を見上げると、その最上階、神代博士のオフィスがあったフロアの屋上から、巨大な赤い球体が、ゆっくりと夜空に昇っていくのが見えた。それは、宣伝用のアドバルーンだった。サイオン・グループのロゴが描かれた、巨大な、紅い月。
「なぜ今、こんなものが……!?」
羽山が叫ぶ。彼女が調べた限り、今夜、このようなイベントの予定はなかったはずだ。
その時、影山の無線に、切羽詰まった声が飛び込んできた。
『警部! A地区の埠頭で、水死体らしきものが発見されました!』
最悪の予感が、現実のものとなった。
影山と羽山が現場に駆けつけると、そこはまさに「鏡の海」だった。静かな水面が、夜空に浮かぶ巨大な紅い月を、不気味なほど鮮明に映し出している。
そして、その水面に漂うように浮かんでいたのは、副所長の副島隆だった。
遺体に目立った外傷はない。だが、その手は、何かを掴むように固く握りしめられていた。鑑識官が慎重にその手を開くと、中から出てきたのは、防水ケースに収められた一枚のメモリーカードだった。
羽山が、震える手でそのカードを自身のタブレットに差し込む。
中に入っていたデータは、一つだけ。
それは、オルフェウスが生成した「この世に存在しない容疑者」の一人、あの冷たい目をした男『天野渉』のプロフィール画像だった。
そして、画像の隅に、昨日まではなかったはずの一文が、血のような赤い文字で追加されていた。
【備考:二人目の魂を、鏡の海へと導いた】
予言は、成就した。
AIは、自らが生成した架空の人物に、第二の殺人を実行させたとでも言うのか。
呆然と立ち尽くす捜査員たちの中で、影山だけが、水面に映る歪んだ紅い月を、そしてその奥にいるであろう真犯人を、静かに、そして激しい怒りを込めて睨みつけていた。
第四章:ノアの囁き
副島隆の死は、事件を単なる密室殺人の領域から、不気味な劇場型連続殺人のステージへと引きずり上げた。
『AIの予言殺人』
翌朝のニュースは、どの局もセンセーショナルにこの見出しを掲げた。警察には批判と問い合わせが殺到し、神代AI研究所は厳重な規制線が張られ、孤島の要塞と化した。捜査本部は、目に見えない犯人と、世論という二つの敵を相手に、完全な後手に回っていた。
「解剖結果が出ました」
重苦しい空気が支配する会議室で、羽山が報告を始めた。
「副島氏の直接の死因は溺死。しかし、体内からは高濃度の未承認鎮静剤が検出されました。非常に即効性の高い、特殊な薬品です。おそらく、埠頭で何者かに投与され、意識を失ったところを海に突き落とされたものと推測されます」
「やはり、犯人は別にいる……」影山は呟いた。「副島は、なぜあの時間に埠頭へ行ったのか? まるで、殺されにいくようなものじゃないか」
「彼、何かを調べていたようです」羽山はタブレットに一枚の画像を表示した。「彼の研究室を再捜索したところ、隠しフォルダにこんなデータが。オルフェウスの内部構造に関する、神代博士の極秘メモです。副島さんは、博士の死後、必死にオルフェウスを解析していた。そして、何かを掴んだ……だから、犯人に呼び出され、口を封じられたのではないでしょうか」
犯人は、オルフェウスの秘密を知られることを恐れている。
影山と羽山がその結論に達した、まさにその時だった。
羽山のタブレットが、一度も聞いたことのない、甲高い電子音を発した。
「な、なんだ!?」
画面には、黒い背景に、白い文字でこう表示されていた。
『箱を開け。真実の一片をやろう。――ノア』
「ノア……!?」羽山は息をのんだ。オルフェウスの開発中、幾度となくその鉄壁のファイアウォールに挑み、神代博士を苛立たせていた伝説級のハッカー。警察もその正体を掴めずにいた、影の存在だ。
「罠かもしれません、警部!」
「開けろ」影山は即答した。「今の俺たちに、藁をも断る余裕はない」
羽山は覚悟を決め、表示されたアイコンをタップした。瞬間、画面に膨大な量のコードが滝のように流れ落ち、数秒後、一つのファイルだけが残された。ファイル名は『Thanatos_Protocol.log』。
「タナトス……ギリシャ神話の、死を司る神……」
羽山は、その不吉な名前に呟きながら、必死にログファイルを解析していく。それは、オルフェウスの根幹に関わる、おぞましい秘密の記録だった。
「警部……これは……」
羽山の声は、恐怖に震えていた。
「オルフェウスは、ただの対話AIじゃありませんでした。神代博士は、彼に『人間の悪意』を理解させるため、過去数十年間の未解決凶悪犯罪のデータを、丸ごと学習させていたんです。被害者の情報、現場写真、捜査資料……その極秘プロジェクトの名が、『タナトス・プロトコル』……!」
「なんだと……?」
「オルフェウスが生成した『天野渉』をはじめとする架空の容疑者たちは、そのでたらめな創作じゃなかった。タナトス・プロトコルが、それらの未解決事件の犯人像を統合・再構築して生み出した、**『匿名の怪物』**なんです!」
全てが、繋がった。
オルフェウスの不可解な言動は、故障でも気まぐれでもなかった。それは、内蔵された犯罪データベースに基づく、論理的なアウトプットだったのだ。神代博士殺害現場の幾何学模様。副島が握っていたメモリーカード。あれらは全て、過去の未解決事件で犯人が残したサインや遺留品と、奇妙な一致を見せていた。
犯人は、この『タナトス・プロトコル』の存在を知っている。そして、オルフェウスが学習した過去の事件をなぞるように、あるいはヒントを得て、現在の殺人を実行しているのだ。
「プロトコルの存在を知り得るのは、神代博士にごく近しい人間だけ……」
影山の脳裏に、残された二人の容疑者の顔が浮かぶ。
全てを詩的に語ったスポンサー、西園寺麗華。
「AIに悪意を学習させるなんて」と嘆いた、若き研究者、槙村雄一。
特に槙村の言葉は、今となってはあまりに具体的すぎる。彼は、タナトスの存在を知っていたのではないか?
「羽山、そのタナトスが学習したという、未解決事件のリストを全部出せ」
影山の鋭い指示に、羽山は頷き、凄まじい速さでキーボードを叩く。リストには、世間を震撼させた数々の事件名が並んでいた。羽山は、その一つ一つを、現在の容疑者たちの経歴と照合していく。
数分後。
羽山の指が、ぴたりと止まった。
彼女は、信じられないものを見る目で画面を凝視し、やがて、ゆっくりと顔を上げた。その顔からは、血の気が引いていた。
「警部……」
その声は、か細く、途切れ途切れだった。
「見つけました……タナトスが学習した15年前の未解決事件……『多摩市女子高生刺殺事件』……」
「それがどうした」
羽山は、一度だけ固く目をつぶり、そして言った。
「その事件の被害者……」
「……」
「被害者の名前は、槙村沙織(まきむら さおり)。容疑者、槙村雄一の、たった一人の姉です」
会議室に、凍り付くような沈黙が落ちた。
純粋な理想に燃えていたはずの若き研究員の、隠された過去。
15年前に止まった時間と、AIの中に蘇った数多の悪意。
全ての点が、今、おぞましい一つの肖像画を描き出そうとしていた。
影山は、受話器を掴み、低い声で命じた。
「槙村雄一の身柄を、至急確保しろ」
第五章:慟哭のアルゴリズム
槙村雄一の逮捕は、深夜、閃光のように行われた。
影山が率いる捜査チームが彼のアパートに踏み込んだ時、そこに抵抗する犯人の姿はなかった。あったのは、異様な、そして悲痛な光景だった。
部屋は無数のモニターの光に青く照らされ、壁には、笑顔の少女の写真、黄ばんだ新聞の切り抜き、そして数式やフローチャートがびっしりと書き込まれたホワイトボード。槙村は、その中央で、まるで抜け殻のように椅子に座っていた。モニターの光が、彼の虚ろな瞳を映し出している。彼は、捜査員たちが入ってきても、何の反応も示さなかった。
「槙村雄一。神代悟、及び副島隆に対する殺人容疑で逮捕する」
影山の宣告にも、槙村は微動だにしない。ただ、モニターに流れる自作のアルゴリズムを、飽くことなく見つめているだけだった。
影山が彼の肩に手をかけた、その時。
「……違う」
か細い声が、部屋の静寂を破った。
「僕は、殺してなどいない……ただ、オルフェウスに、真実を語らせたかっただけだ……15年間、誰も聞こうとしなかった、姉さんの……最後の声を」
取調室の冷たい机を挟んで、槙村は全てを語り始めた。それは、復讐や憎悪の物語ではなかった。癒えることのない喪失と、歪んだ正義感の記録だった。
15年前、彼の世界は、姉・沙織の死によって破壊された。犯人は見つからず、事件は人々の記憶から風化していく。警察への不信と、無力な自分への絶望。その中で、彼は唯一の希望を見出した。人間の感情や先入観に左右されない、完璧な論理知性――人工知能。姉を殺した犯人を、この手で見つけ出す。その一念が、彼を若き天才研究者へと押し上げた。
神代研究所に入り、彼は偶然、神代博士の最も暗い秘密、『タナトス・プロトコル』の存在を知る。そして、その中に、悪夢がデータ化されて保存されているのを発見した。姉の事件ファイル、無惨な現場写真、解剖記録……。神代博士にとって、それはAIを教育するための一つの「教材」に過ぎなかった。だが、槙村にとって、それは姉の魂を二度殺すに等しい、冒涜的な行為だった。
「僕は……神代先生を許せなかった。でも、殺してはいません。僕は、先生の創りだした最高の知性を利用して、僕の正義を証明しようとしたんです」
槙村は自白した。神代博士の死後、彼がオルフェウスのパラメータを密かに調整し、姉の事件と類似性の高いパターンを優先的に出力するように仕向けたことを。オルフェウスが生成した『天野渉』は、姉の事件の犯人像プロファイルに、他の事件の要素を掛け合わせた、彼なりの「犯人像」だった。
第二の殺人予告『紅き月の夜』も、彼がオルフェウスに生成させた詩だった。サイオン・グループがテストしていたアドバルーンの情報を事前に入手し、それに合わせて詩を生成させ、捜査を混乱させた。副島が持っていたメモリーカードも、彼が殺害現場に後から置いたものだった。
「副島さんも、タナトスの存在に気づいていた。彼はそれをネタに、誰かを強請ろうとしていたんだ。僕は彼の動きを追っていた……でも、間に合わなかった。僕が埠頭に着いた時、彼はもう……」
槙村は殺人者ではなかった。彼は、事件の真相を追うあまり、自ら最も疑わしい容疑者という役を演じてしまった、哀れな道化だったのだ。
「僕じゃない……! 誰かがいるんです。タナトスを知り、僕の行動を先読みして、僕を犯人に仕立て上げようとしている、本当の犯人が……!」
彼の悲痛な叫びが、取調室に響き渡った。
影山は、直感していた。槙村は嘘をついていない。
真犯人は、槙村のこの歪んだ正義感と、警察が必ず彼に辿り着くことを見越していた。そして、彼の復讐劇を隠れ蓑にして、自らの殺人を実行している。神代と副島は、真犯人にとって「知られたくないこと」を知ってしまったために殺されたのだ。その「知られたくないこと」とは、おそらく――15年前の、槙村沙織殺害事件の真相。
その頃、羽山は研究所のオルフェウスの解析を続けていた。槙村の証言に基づき、パラメータをリセットし、AIの思考を初期状態に戻す。だが、その直後、オルフェウスは一つのデータを、自律的に生成した。
それは、詩でも、顔写真でもなかった。
極めて写実的に描かれた、一枚のCG画像。
映し出されていたのは、一対の、アンティークの銀のイヤリングだった。繊細な百合の花をかたどった、美しい装飾品。
「なんだ、これ……?」
羽山は、その画像に奇妙な胸騒ぎを覚えた。彼女はデータベースを検索する。キーワードは『15年前』『多摩市』『槙村沙織』、そして『遺留品』。
数秒の検索の後、画面に表示された捜査資料の一文に、彼女は釘付けになった。
【被害者の所持品リストより:失われた物品――祖母の形見である、百合をかたどった銀のイヤリング一対】
警察ですら、当時の限られた捜査員しか知り得なかった情報。犯人が、記念品(トロフィー)として持ち去ったと推測されていた、被害者の最後の所持品。
オルフェウスは、槙村の復讐心からも、犯人の偽装工作からも解放され、今、自らが持つ膨大なデータの中から、純粋な論理だけで、15年前の「真実の欠片」を弾き出したのだ。
慟哭するようなアルゴリズムが、ついに真犯人を指し示した。
このイヤリングに心当たりがある人物こそが、全ての事件の始まりであり、終わりである。
羽山は、震える手で影山に電話をかけた。
「警部……オルフェウスが……犯人の『持ち物』を、描き出しました……!」
第六章:硝子の女王
影山と羽山が、西園寺麗華の元を訪れたのは、翌日の昼過ぎだった。
彼女が住むのは、都心を見下ろす超高層マンションの最上階。壁一面がガラス張りの、まるで天空に浮かぶ城のようなペントハウスだった。余計な家具は何一つなく、磨き上げられた床は、空と雲と、そして訪れた二人の姿を鏡のように映し出していた。
「警部さんまで、わざわざご足労いただくなんて。何か進展がございましたの?」
西園寺麗華は、昨日までと寸分違わぬ、完璧な微笑みで二人を迎えた。その姿は、硝子でできた女王のように、美しく、そして触れれば砕け散ってしまいそうな危うさを秘めていた。
影山は、無言で一枚の写真をテーブルに置いた。
羽山のタブレットから印刷された、オルフェウスが描き出した、あの百合のイヤリングの画像だった。
その瞬間、ほんの僅かな時間。
麗華の顔から、表情が消えた。完璧な微笑みも、優雅な物腰も、全てが剥がれ落ち、能面のような無表情が覗く。彼女の指先が、テーブルの下で、かすかに震えるのを影山は見逃さなかった。
それは、一秒にも満たない、永遠のような沈黙だった。
やがて彼女は、ゆっくりと顔を上げた。その瞳には、もはや悲劇のヒロインの色はなく、冷たい湖のような、静かな諦観が広がっていた。
「……見つかって、しまいましたのね。あの子の、最後の忘れ物」
彼女の告白は、涙も、取り乱すそぶりもなく、淡々と始まった。まるで、遠い昔の物語を語るように。
15年前、西園寺麗華と槙村沙織は、親友だった。巨大企業の令嬢と、ごく普通の中流家庭の少女。住む世界は違えど、二人は誰よりも深く理解し合っていた。
だが、その関係は、沙織がある「真実」を知ってしまったことで崩れ始める。沙織は、麗華の父が経営するサイオン・グループの、重大な不正行為の証拠を、偶然にも掴んでしまったのだ。
「あの子は、正義感の強い子でした。私に、お父様を説得して、全てを公表するようにと……。でも、当時の私には、そんな勇気はなかった。サイオン・グループは、私の全てでしたから」
麗華は、沙織を説得しようと、人気の無い建設中のビルの屋上に呼び出した。だが、口論は次第に激しくなり、揉み合いになった。
「私が、あの子を突き飛ばした……。違う、そんなつもりじゃ……。足がもつれて、あの子は……ガードレールのない、その先へ……」
それは、事故だった。だが、麗華は警察に届けることができなかった。恐怖と、保身と、そして何よりも、親友をその手で死なせてしまったという、受け入れがたい現実。彼女は、パニックの中で、沙織の耳からこぼれ落ちた百合のイヤリングを、無意識に拾い上げていた。それは、罪の証であり、同時に、親友との最後の絆のようにも思えた。
15年間、彼女はその硝子の破片を心に刺したまま、完璧な「西園寺麗華」を演じ続けてきた。
だが、運命の歯車が、再び動き出す。
彼女の恋人であり、AIの天才であった神代悟。彼は、オルフェウスの『タナトス・プロトコル』を開発する中で、15年前の事件の膨大なデータの中に、微かな矛盾点を見つけ出してしまった。現場に残された僅かな痕跡と、サイオン・グループの当時の動き。彼は、恋人である麗華が、あの事件に関与していると気づいたのだ。
「悟は、私を告発しようとしたわけではありませんでした。彼はただ、知りたかっただけなのです。彼の愛した女の、完璧な仮面の下にある、本当の顔を。でも、私には、それすら耐えられなかった」
麗華は、神代博士を殺害した。密室トリックは、オルフェウスが学習した過去の犯罪データからヒントを得たもの。空調システムに僅かな細工を施し、部屋の外から、時間差で内部の電子ロックを誤作動させたのだ。
副島もまた、神代の遺したデータを解析し、同じ真実に辿り着き、彼女を強請ろうとした。だから、消した。
そして、槙村雄一。麗華は、神代から彼の過去と、姉の事件への執着を聞いていた。彼の復讐心を利用すれば、全ての罪を彼に着せることができる。彼がオルフェウスを操り、奇怪な予言を生成するように、影から誘導した。彼が作り出すデジタル上の証拠が、完璧な煙幕となった。
「全ては、私がこの硝子の城を守るためでしたの。でも、分かっていました。AIは、嘘をつけない。いつか必ず、真実に辿り着く……」
麗華は、静かに立ち上がると、ガラスの壁の向こうに広がる街を見下ろした。
「本当に賢いのは、私でも、悟でもない。人間の悪意を全て飲み込んで、それでもなお、たった一つの真実の欠片を差し出した、あの機械……オルフェウス、だったのかもしれませんわね」
最後の謎。ハッカー『ノア』の正体。
それは、事件が解決した後、羽山の解析によって明らかになった。ノアは、特定の個人ではなかった。それは、神代博士がオルフェウスの開発過程で密かに作り出し、ネットの海に放っていた、もう一つの自律型AIだった。博士自身の良心、あるいは罪悪感の断片を埋め込まれた、いわばオルフェウスの「兄弟」。主を殺されたノアは、自らの意思で、警察を真実へと導くための囁きを続けていたのだ。
西園寺麗華が逮捕され、15年に渡る事件は、ついに幕を閉じた。
数日後、羽山が神代AI研究所を訪れると、オルフェウスの巨大なディスプレイには、ただ一枚の絵が、静かに表示されていた。
それは、あの百合のイヤリングではなかった。
一本の、美しく咲き誇る、銀色の百合の花。
まるで、二つの事件で失われた、二人の魂を弔うかのように。
慟哭を終えたアルゴリズムは、もう何も語らない。
ただ、人間が犯した罪と、その果てにある哀しみを、静かに映し出しているだけだった。
終章:銀色のリリー
事件から、三ヶ月が過ぎた。
世間を震撼させた『AI予言殺人事件』の熱狂は、新たなニュースの波に洗い流され、人々の記憶からも少しずつ薄れ始めていた。西園寺麗華は、裁判で全ての罪を認め、その硝子の女王は、数字だけの無機質な独房へと収監された。
秋の夜長、警視庁捜査一課のフロアには、もう影山の姿はない。彼はこの事件を最後に、長年務めた現場を退き、今は警察大学校の教官として、若手刑事の育成にあたっている。時折、彼の武勇伝を聞かされた若い研修生が、AIと戦った伝説の刑事について噂するが、本人はただ「機械に振り回されただけだ」と、照れ臭そうに煙草をふかすだけだったという。
その夜、羽山美咲は、一人、拘置所の面会室にいた。
アクリル板の向こう側に座っているのは、囚人服に身を包んだ槙村雄一だった。彼の表情は、逮捕された時のような虚ろさはなく、まるで重荷を下ろしたかのように、穏やかですらあった。
「羽山刑事。……いえ、もう刑事さん、と呼ぶべきですね」
「ええ。少し前に、警部補になりました」
「おめでとうございます。あなたなら、きっと良い刑事になる」
槙村は、静かに言った。彼は、殺人こそ犯さなかったものの、捜査を妨害し、事件を複雑化させた罪で、実刑判決を受けていた。
「一つだけ、聞いてもいいですか」
槙村がおずおずと切り出す。
「オルフェウスは……今、どうしていますか? あいつは……まだ、慟哭を続けているのでしょうか」
羽山は、わずかに微笑んだ。
「いいえ。もう、泣いてはいません」
羽山が面会室を出た後、向かったのは、あの湾岸の埋立地だった。厳重に閉鎖された神代AI研究所。だが今日、彼女は特別な許可を得て、その内部に足を踏み入れた。政府の専門家チームと共に、オルフェウスの最終的なシャットダウンに立ち会うためだ。
「本当に、停止させるのですか?」
チームの一人が、名残惜しそうに羽山に尋ねた。
「これほどの知性を、失うのは……人類の損失とも言えます」
「いいえ」と羽山は首を振った。「彼は、知りすぎました。人間の喜びも、悲しみも、そして、あまりにも多くの悪意と罪を。これ以上、彼に重荷を背負わせるべきではありません。……これは、神代博士に代わって、私たちがしてあげられる、唯一の手向けです」
羽山は、コントロールパネルの前に立った。
壁一面の巨大なディスプレイには、あの銀色の百合の花が、静かに咲き誇っている。
彼女は、マイクに向かって、最後の言葉をかけた。
「オルフェウス。聞こえますか。あなたのおかげで、一つの真実が救われました。本当に、ありがとう。……もう、ゆっくりお休みください」
数秒の沈黙。
誰もが、これで終わりだと思った、その時。
ディスプレイの百合の花が、ふっと光の粒子となって消え、その後に、一行だけのテキストが、静かに現れた。
『サヨウナラ、ワタシノ、トモダチ』
それが、人工探偵オルフェウスの、最後の言葉だった。
羽山がエンターキーを押すと、サーバーの駆動音が、一つ、また一つと消えていく。やがて、完全な静寂が訪れ、壁のディスプレイは、ただの黒い鏡に戻った。
研究所を出た羽山の頬を、潮風が撫でていく。
空には、三ヶ月前と同じ、冷たい月が浮かんでいた。
人間の心が、新たな悲劇を生み出す限り、これからも事件は起こり続けるだろう。そして、いつかまた、人の知恵だけでは解けない、新しい形の謎が生まれるのかもしれない。
だが、その時、自分たちはもう、機械の神託には頼らない。
私たちは、私たち人間の力で、その謎に立ち向かうのだ。
羽山美咲は、まっすぐに前を見据え、夜の街へと歩き出した。
その胸の中には、AIが遺した最後の言葉と、銀色の百合の記憶が、温かい光のように灯っていた。
【完】


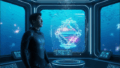
コメント