この物語はフィクションです。現実の社労士の権限については各種法令のご確認をお願いいたします。
序章:三十六協定のインク
神崎法子は、インクの匂いが嫌いではなかった。特に、真新しい契約書の上を滑る万年筆のペン先から、じわりと紙に染み込んでいく、あの微かな青の香り。それは、約束が形を得る瞬間の匂いであり、これから始まる関係性の重さを予感させる匂いだった。
だが今、彼女の鼻腔をくすぐっているのは、それとは似て非なる、もっと乾いた、もっと無機質な匂いだった。レーザープリンターが高熱でトナーを定着させた、消耗品の匂い。渋谷のスクランブル交差点を見下ろすガラス張りの会議室で、彼女の前に差し出された数枚の書類は、その匂いをあたりに放っていた。
「こちらが、弊社と神崎先生との顧問契約書になります。内容をご確認の上、ご署名を」
声の主は、伊達俊介。株式会社ネクスト・シフトの人事部長だ。磨き上げられたマホニーのテーブルの向こう側で、彼は完璧な角度の笑みを浮かべている。イタリア製の高級スーツは、彼の鍛えられた身体のラインを寸分の狂いもなく描き出し、手入れの行き届いた指先が、書類の端を軽くつまんでいる。
「かつては私も、コードを書く側の人間でしてね。理想のプロダクトのためなら、時間など忘れて没頭したものです。夜も昼もなく、ただ最高のものを創り出すことだけを考えていた」
伊達は、窓の外の喧騒に目をやりながら、ふと遠い目をした。
「ですが今は、守る側。法と現実という、二つの異なる言語を翻訳し、組織のパフォーマンスを最大化するのが私の仕事です。時には、非情な判断も必要になりますがね」
隙のない物腰の中に、微かに覗く過去の自負と、目的のためなら手段を選ばないという冷徹な哲学。法子は、彼が単なる管理職ではないこと、そして、一筋縄ではいかない交渉相手になることを見抜いた。
法子は、契約書に署名を終えると、伊達が差し出したもう一部の書類に目を移した。
「それから、こちらが現在の弊社の『時間外労働・休日労働に関する協定書』、いわゆる三十六(サブロク)協定の写しです」
来たか、と法子は内心で息を呑んだ。社会保険労務士が新しい顧問先と契約する際、まず初めに確認すべき、企業の「素顔」がそこにはある。
A4用紙に印刷された協定書は、一見、どこにでもある雛形だった。事業の種類、業務の種類、労働者数。そして、最も重要な「延長することができる時間」の欄。
「特別条項付き、ですね。時間外労働と休日労働の合計で、単月では100時間未満、年間の上限は720時間。法規定のギリギリに設定されています」
法子は淡々と告げた。働き方改革関連法によって定められた、時間外労働の絶対的な上限。それは、働く者を守るための防波堤であると同時に、企業にとってはここまでなら働かせてもよいという免罪符にもなり得る。
(……複数月平均80時間以内の要件も記載上はクリアしている。協定書自体に、法的な瑕疵はない。だが、この完璧すぎる数字の裏には、おそらく裁量労働制の巧妙な運用があるはずだ)
法子の視線は、協定書の最下部に吸い寄せられた。労働者の過半数を代表する者として署名している人物の名前。
「この、高橋翔太さん、という方は」
「弊社のリードエンジニアです。先日、従業員投票という民主的な手続きを経て、労働者代表に選出されました。会社の宝ですよ」
伊達は淀みなく答えた。だが、その「民主的な手続き」という言葉が、妙に芝居がかって聞こえた。
そして、法子は気づいた。高橋翔太の名前。他の文字がレーザープリンターでシャープに印刷されているのに対し、その部分だけが、まるで一度消された文字の上に、無理やり新しい名前を重ねて印刷したかのような、奇妙な濃淡と紙の微かな毛羽立ちがあった。
「何か、気になりますか?」
伊達の鋭い声が、法子の思考を中断させた。
「いえ……」法子は、ゆっくりと顔を上げた。「この協定が締結されたのは、半年前ですね。そろそろ、次の協定更新の準備も始めなければなりません。その際は、労働者代表の選出プロセスから、改めて適正な手続きを踏むお手伝いをさせていただきます」
それは、社労士としての正論であり、同時に、伊達に対する牽制だった。
伊達の目が、初めて笑み以外の光を宿した。面白い、とでも言うような、値踏みするような光。
「それは心強い。ぜひ、先生のお力をお借りしたい」
契約から、一ヶ月が過ぎた。
法子は、ネクスト・シフト社の労務データと格闘する日々を送っていた。表面的には、どこにも問題はない。だが、あのインクの滲みが、小さな棘のように法子の心に引っかかり続けていた。
その報せが届いたのは、冷たい雨が渋谷の街を濡らす、月曜日の朝だった。
「神崎先生、落ち着いて聞いてください」電話の向こうの伊達の声は、狼狽を装っていた。「先日お話しした、エンジニアの高橋翔太君が……昨夜、自宅で亡くなりました」
法子は、息を呑んだ。
「変死事案として所轄が一時調査しましたが、外傷や第三者の介入を示す直接的な証拠は見当たらず、事件性は低いとの判断です。ただ、過労の可能性も完全に否定はできないため、現在は労働基準監督署が情報を引き継ぎ、調査を進めている段階にあります」
伊達の淀みない説明を聞きながら、法子の頭の中では、あの協定書がフラッシュバックしていた。インクの滲んだ、労働者代表の名前。
彼の死は、本当に自ら選んだものなのか。それとも――。
神崎法子の、社労士としての本当の仕事が、今、始まろうとしていた。
第一章:偽装されたタイムカード
ネクスト・シフト社のオフィスは、死の匂いがしなかった。
それが、神崎法子が最初に抱いた強烈な違和感だった。警察の事情聴取が終わり、フロアには社員たちが戻っていたが、誰も高橋翔太の死について語らう者はいない。誰もがヘッドフォンで外界の音を遮断し、目の前のディスプレイに没頭している。まるで、一人の人間の死など、システムからバグが一つ取り除かれた程度の出来事だとでも言うように。
応接室に通された法子を待っていたのは、所轄の刑事・安西と、いつもと変わらぬ完璧なスーツ姿の伊達だった。
「……という訳で、現時点では事件性を示す物証は何もない。変死事案は山ほどあるんでね。これ以上は、我々ではなく、労基さんの仕事だ」
安西は、面倒そうに言い捨てて部屋を出て行った。その背中に、法子は何か言いたげな視線を送ったが、言葉にはならなかった。
「神崎先生」残された伊達は、弱々しい表情を作って見せた。「会社として、彼の死は痛恨の極みです。しかし、これがもし『労災』ということになれば……。先生にお願いしたいのは、我々の労務管理に一切の瑕疵がなかった、という客観的なレポートの作成です」
それは依頼の形をとりながら、暗に「会社の望む結論を出せ」と命じる、冷たい圧力だった。
その夜、法子は事務所で、ネクスト・シフト社の勤怠管理システムにログインしていた。画面に表示された高橋翔太の勤怠記録は、伊達が言った通り、完璧だった。月間の時間外労働時間は、最も多い月でも七十五時間。協定の上限内に、見事に収まっている。
完璧すぎる。法子の指が、無意識にトラックパッドの上を滑る。人間が働く以上、そこには必ず「揺らぎ」が生じる。高橋の記録には、そうした生身の人間の痕跡が、あまりに希薄だった。
法子は、社労士試験の勉強をしていた頃のテキストを思い浮かべた。労働時間の定義。それは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指す。たとえタイムカードが押されていなくとも、業務に従事していれば、それは労働時間と見なされる。
おそらく、この完璧な勤怠記録は、専門業務型裁量労働制を隠れ蓑にした、巧妙な偽装だ。裁量労働制は、決して「残業代ゼロの魔法の杖ではない」。深夜・休日割増は別途発生するし、会社は労働者の健康・福祉を確保する措置を講じる義務がある。
もし、高橋がタイムカードを押した後も、「見えない労働時間」に従事していたとしたら?
翌日、法子は再びネクスト・シフト社を訪れていた。
「伊達さん。勤怠記録は、確かに拝見しました。法的な問題は見当たりません。ですが、レポートを作成するにあたり、彼のPCのログオン・ログオフの記録も拝見できますね?」
その瞬間、伊達の顔から表情が消えた。完璧な能面のように、全ての感情が削ぎ落とされた。
「……承知いたしました。もちろん、お渡ししますよ。我々には、何一つ、隠すことなどありませんから」
彼の瞳の奥で、冷たく、硬質な光が揺らめいたのを、神崎法子は決して見逃さなかった。
その日の深夜、事務所で一人、報告書の草案を練っていた法子の元に、非通知設定の電話がかかってきた。
『……神崎、法子先生、でしょうか』
くぐもった、若い男の声。囁くように、そして何かに怯えるように、その声は震えていた。
『高橋のこと……調べないでください。あなたも……消されますよ』
一方的に、電話は切れた。
ツーツー、という無機質な切断音。法子は、受話器を握りしめたまま、しばらく動けなかった。背筋を、冷たい汗が伝う。恐怖。だが、それ以上に、腹の底から、冷たい怒りが湧き上がってきた。
消される? 誰に?
この事件は、単なる過労自殺ではない。その背後には、誰かの明確な「殺意」が隠されている。
法子の脳裏に、あのインクの滲みが、今度は血痕のようにじわりと広がっていく。偽装されたタイムカードの向こう側で、一人の青年が殺されたのだ。
ならば、こちらも法で戦うまで。
社会保険労務士、神崎法子の、本当の戦いが始まった。
第二章:沈黙の産業医
伊達から送られてきたPCのログデータは、法子の予想通り、勤怠記録と完全に一致していた。あまりに不自然な一致。法子は、専門家の力を借りる前に、自らログファイルのプロパティを調べたが、巧妙に処理されており、素人が手を出せる領域ではなかった。
直接的な証拠で追い詰めるのが不可能ならば、攻め手を変えるしかない。
法子は、思考の軸足を「労働時間」から「安全配慮義務」へと移した。彼の精神的な不調を会社が知りながら放置していたとすれば、この義務違反を問うことができる。
その鍵を握るのが、「産業医」の存在だ。ネクスト・シフト社は従業員数98名。常時50人以上の労働者を使用する事業場として、産業医の選任義務がある。
契約書類から探し出した産業医・小田切譲のクリニックは、閑静な住宅街にあった。
塵一つない待合室には、クラシック音楽が静かに流れている。診察室に通された法子を迎えた小田切は、白髪を綺麗に整え、温和な笑みを浮かべた初老の紳士だった。
「神崎先生ですね。伊達さんから、お話は伺っております。……高橋君の件、誠に残念です」
その表情に嘘の色は見えない。法子は、まず当たり障りのない労務相談から話を始め、徐々に本題へと切り込んでいった。
「ところで先生、御社では昨年もストレスチェックを実施されていますね。その結果について、少し……」
「お気持ちは分かりますが、神崎先生」小田切は、法子の言葉を遮った。「ご存知の通り、私には医師としての守秘義務があります。個別の面談内容について、ご本人様の明確な同意なく第三者にお話しすることはできません」
職業倫理に裏打ちされた、完璧な正論だった。
「もちろん、承知しております。ですが、先生」法子は、視線を鋭くした。「労働安全衛生法に基づき、高ストレス者との面談後、先生が会社にご提出されたはずの面接指導結果報告書が、先日頂いた労務監査資料の中に見当たらないのです。会社側で紛失された可能性も考えられますが、先生のお手元に控えなどはございませんでしょうか?」
法子の具体的な指摘に、小田切の表情が微かにこわばった。彼が動揺したのは、「面談の有無」ではなく、「提出したはずの書類の不在」を突かれたからだ。
「……さあ。提出は、したはずですが。会社側の管理の問題ではないですかな」
彼は平静を装って切り返した。だが、法子にはその一瞬の動揺で十分だった。彼が何かを隠しているか、会社が意図的に隠蔽している。その確信を得た直後、事務所に戻った法子の元に、匿名の協力者から、最初のメールが届いた。
Project: Chimera
その単語と、高橋が死んだ日がプロジェクトのデッドラインだったことを示す画像が、法子を新たな謎へと引きずり込んだ。
第三章:キマイラの残響
「キマイラ・プロジェクト」は、人間の記憶を操作する、禁断の脳科学研究だった。ホワイトボードの写真に記された「記憶データ同期エラー」の文字が、その危険性を物語っていた。
法子は、高橋翔太の過去を遡る。社労士として正規に取得した「被保険者記録照会回答票」で、彼の職歴に半年間の空白があることを突き止めた。
答えは、千葉の実家で会った、彼の両親が持っていた。
「あの子は……前の会社で心を病んでしまって……」
母親は、憔悴しきった顔で、翔太の子供の頃のアルバムを見せてくれた。そこには、はにかみながら笑う、ごく普通の青年の姿があった。
「再就職が決まった時は、本当に嬉しそうで……。でも、最近は、『僕のせいで、会社の人に迷惑をかけてしまった』なんて、よく分からないことを言って、思い詰めているようでした」
法子が、療養中の生活について尋ねると、母親は戸棚の奥から、一枚の古い封筒を取り出してきた。
「なんだかよく分からないけど、大事な書類だからとっておきなさいって、あの子が……」
それは、「傷病手当金支給決定通知書」の控えだった。半年間の療養。ネクスト・シフト社は、彼のその経歴を知り、弱みとして握っていたに違いない。
その夜、事務所に戻った法子は、私立探偵・桐島圭吾に連絡を取った。元警視庁サイバー犯罪対策課のエース。もはや、社労士の領域を超えている。
「なぜ警察ではなく俺なんだ?」
「警察が動かない『グレー』な部分を暴けるのは、あなたしかいない。伊達俊介と小田切譲。この二人を調べて」
法子が桐島と電話を切った直後、事務所のドアの郵便受けに、無地の封筒が投函された。中には、USBメモリ。匿名の協力者からだ。おそらく、莉奈が軟禁される前に、友人に託していた最後のバックアップだろう。
ヘッドフォンを装着し、音声データを再生する。
『……伊達さん、もう無理です! あのテストは、危険すぎます!』
『落ち着け、高橋君。……君はもう、ただのエンジニアじゃない。**共犯**なんだよ』
伊達の、氷のように冷たい声。高橋は、会社の犯罪行為の片棒を担がされ、良心の呵責と恐怖から逃れようとしていたのだ。そして、消された。
これは、殺人事件だ。法子は、確信した。
第四章:不協和音の解雇予告
翌日、法子は高橋の両親から、一人の女性の名前を聞き出す。佐伯莉奈。高橋が唯一、悩みを相談していた同僚。しかし、彼女はひと月前に会社を辞めていた。
事務所に戻った法子に、桐島からの第一報が入る。それは、詳細な調査報告書としてメールで送られてきた。
「音声データは本物だ。それと、小田切のクリニックは、ネクスト・シフト社がペーパーカンパニー経由で実質的に所有している。奴らはグルだ」
報告書には、複雑な資本関係図も添付されていた。
「さらに、伊達からあんたに送られたPCログだが、デジタルフォレンジックにかけた。データそのものは消えているが、**管理者権限でファイルが操作された『痕跡』がタイムスタンプ付きで残っている。**これも立派な証拠になる」
その時、協力者から最後のメールが届いた。莉奈が伊達から脅迫的な退職勧奨を受けた際の面談記録。そして、「彼女を助けて」という悲痛なメッセージ。それは、彼女が身の危険を感じ、軟禁される直前に、最後の望みを託して自動送信予約していたメールだった。
「先生、まずい!」桐島から緊急の電話が入る。「莉奈の居場所を特定したが、伊達の手の者に軟禁されている!」
法子は、事務所を飛び出した。
第五章:被保険者の証言
桐島の助けを借り、法子はアパートに囚われていた莉奈を辛くも救出した。桐島のセーフハウスで、莉奈は全てを告白した。
「キマイラは、被験者のトラウマ記憶をAIが消去するシステム。でも、事故で被験者の人格が破壊された。私と高橋君は告発を決意し、そして……」
伊達は、高橋のうつ病の既往歴を利用し、自殺に見せかけて殺害する計画を立てたのだ。莉奈の証言によれば、高橋はサーバー室で薬物を投与され、意識を失った後、伊達の息のかかった人間に自宅まで運ばれ、そこで命を絶ったように偽装されたのだという。
「伊達のアリバイを崩す証拠があります」
莉奈は、会社の記録に残らない機密サーバー室の入退室ログのコピーを、クラウドに隠していた。だが、パスワードが分からない。ヒントは「彼が守りたかった、最初の約束」。
法子の頭に、ある言葉が閃いた。それは、高橋が莉奈にだけ、冗談めかして語った、彼が学生時代に初めて作ったプログラムのコードネームだったという。
「彼、言ってたんです。『僕の原点は、これなんだ。たった一行のコードだけど、僕が初めて誰かのために作った、約束のプログラム』って……その名前が……」
莉奈が思い出したその言葉を、法子が打ち込む。
Asu_no_Houteikyuujitsu
(明日の法定休日)
ロックが解除され、伊達のアリバイを完璧に崩す入退室ログが現れた。高橋の退室記録は、そこには無かった。
勝利を確信した瞬間、桐島が叫んだ。
「奴らだ! PCに仕込まれたGPSで、居場所がバレた!」
ビルに追手がなだれ込んでくる。桐島が時間を稼ぐ中、法子は莉奈を連れ、裏口から脱出した。横浜の暗い埠頭での絶体絶命の逃走劇。その二人を救ったのは、一台の黒いセダンだった。運転席には、労働基準監督署の監督官・安西が座っていた。
「桐島という探偵から、あんたが危ないと連絡があった。労基署も、あの会社の異常な労災申請率の低さを内々にマークしてたんだ。……どうやら、ただの自殺じゃなかったらしいな。乗れ!」
第六章(最終章):告発のタイムカード
翌朝、ネクスト・シフト社の役員会議室。安西が「労働安全衛生法違反の疑いに関する、緊急の行政指導」という名目で、伊達と役員全員を招集した。外には、警察が待機している。
法子は、安西のバーで夜通し練り上げた作戦通り、社労士として最後の監査を始めた。
彼女は、証拠を一つずつ、冷静に、しかし、一分の隙もない論理で突きつけていく。改竄の「痕跡」が残るPCログ。隠蔽された産業医の面談記録。佐伯莉奈の証言。そして、伊達のアリバイを崩す機密サーバー室の入退室ログ。
だが、伊達は「全て捏造だ」と一蹴し、動じない。役員たちの間にも、安堵の空気が流れる。
法子は、最後の一撃を放った。それは、殺人の直接証拠ではない。だが、彼の「完璧な仮面」を剥がす、最後の一撃だった。
「伊達さん。あなたは労務管理のプロだ。ならば、お答えいただきたい。なぜ、高橋翔太さんの入社時の標準報酬月額は、彼の実際の給与額から算定される等級よりも、不自然に低く設定されていたのですか?」
その瞬間、伊達の顔から、完璧な仮面が、音を立てて剥がれ落ちた。
それは、彼の病歴を隠蔽するために、彼自身が犯した、専門家としての、唯一の、そして致命的な偽装工作だった。それは、殺人との直接の繋がりはない。だが、役員たちの前で、「この男は、会社の利益のためなら、平然と法を破り、記録を偽装する人間だ」という事実を、動かぬ証拠として証明した。他の証拠の信憑性が、その一撃で、絶対的なものに変わったのだ。
彼は、答えられなかった。長い沈黙。やがて、彼は崩れるように椅子に座ると、乾いた笑いを漏らした。
「……偉大な進歩には、犠牲がつきものだ。君たち凡人には、わかるまい」
その言葉を最後に、捜査員たちが、会議室になだれ込んできた。
終章:夜明けの就業規則
数週間後。
神崎法子の事務所には、以前と変わらない日常が戻っていた。テレビや新聞は、ネクスト・シフト社の驚くべき事件の顛末を、連日報じている。「キマイラ・プロジェクト」は、国の厳しい調査のもと、完全に凍結された。
桐島は、追手との乱闘で腕を骨折したものの、先週、無事に退院し、法子の事務所に高額な請求書を届けに来ては軽口を叩いている。佐伯莉奈は、法子の事務所で事務作業を手伝いながら、新しい人生を歩み始めていた。
ネクスト・シフト社は、経営陣が刷新され、法子が労務顧問として後見する形で、再生の道を歩み始めていた。失墜した信用を取り戻す道は、長く、険しいだろう。
その日、法子は、ネクスト・シフト社の新しい就業規則の最終確認を行っていた。労働時間、休日、賃金。全ての条文が、法に則り、そして働く者の視点に立って、作り直されている。
法子は、その規則の、一番最後のページに、新しい一条を加えた。
第108条(生命と尊厳への配慮)
会社及び、会社に所属する全ての従業員は、企業のいかなる利益活動、あるいは業務上の理由があろうとも、人の生命と、その人間としての尊厳を、他の何よりも優先しなければならない。
それは、法律上の効力も、罰則もない、ただの理念に過ぎない条文だった。
だが、法子には、これが、高橋翔太が本当に守りたかった「約束」の形であると思えた。
窓の外が、白み始めている。渋谷の街が、新しい朝を迎えようとしていた。
法子は、万年筆を置くと、夜明けの光が差し込むオフィスで、その最後の条文を、静かに見つめていた。
知識は、盾にも、刃にもなる。
ならば、自分は、これからも盾を使い続ける者でいよう。冷たい条文の向こう側にある、一人ひとりの人間の、温かい心を守るために。
社会保険労務士、神崎法子の戦いは、まだ始まったばかりだった。
(了)

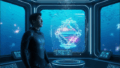
コメント